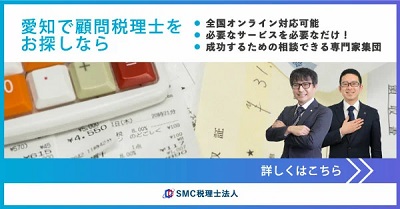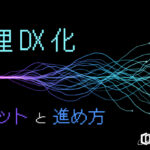この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。
2022年4月19日、最高裁判所第3小法廷で相続に関わる業界の人たちから注目されていた判決が下されました。要約すると「過度な不動産節税に警鐘を鳴らす」司法判断です。
この記事では裁判の経過や判決内容を踏まえながら、これから気を付けるべき相続税対策について解説します。
裁判の経過と問題になった事項
この裁判が注目された最大の理由が、 これまで節税対策の定番ともいえる扱いだった「不動産を利用した節税」に待ったをかけた国税当局の判断の是非が争われたからです。
この節税方法は税理士だけではなく、不動産屋や金融機関も積極的に関与していたことから、現在進行形で節税対策を行っていた多くに人に影響を与えます。
まずは本裁判の経過を追いながら、この節税対策のどこに問題があったのかを考えてみましょう。
ある相続税の申告と税務署の更正処分
平成24年6月17日に資産家だったAさんが94歳で亡くなりました。相続人は3名で平成25年3月に相続税の申告を行ったのですが、課税価格の合計は2,826万円とされたため、相続税の基礎控除内に収まり相続税の総額は0円という内容でした。
ところが平成28年4月27日付けで札幌南税務署が更正処分(申告内容に誤りがあると判断された場合、税務署が納税額の修正もしくは決定をする手続き)と、それに伴う賦課決定処分を相続人に対し行いました。
それにより0円だった相続税が約2億4,050万円とされ、相続人らは国税不服審判所へ処分取消しを求めましたが請求が棄却されました。そして東京地裁に訴え最高裁まで争われました。
Aさんが行っていた節税対策
最高裁の判決文にも書かれていますが、相続税対策を行わなかった場合「本件相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであった」ものを、Aさんはどのように圧縮したのでしょうか。
それは富裕層の相続税対策として定番ともいえる、いわゆる「タワマン節税」でした。現金を6億円相続したら課税価格はそのまま6億円ですが、この6億円でマンションを購入したらどうなるでしょうか。
相続財産の計算をするとき、通常「土地」は路線価で評価し「建物(マンション)」は固定資産税評価額で評価します。不動産が賃貸用に供されていれば、借地権割合や借家権割合でさらに評価が下がります。
これのどこにせつ節税要素があるかといえば、ほとんどの不動産は実勢価格の方が大幅に高く、相続税評価額は時価よりも低くなる点です。ちなみにAさんが購入した2件のマンションの購入価格と、相続税申告時の価額は次のとおりです。
|
購入価格 |
申告価額 |
差額 |
| 杉並区 |
837,000千円 |
200,040千円 |
▲636,960千円 |
| 川崎市 |
550,000千円 |
133,660千円 |
▲416,340千円 |
実に10億円以上の節税効果になります。これだけを見ると「それでも3億円以上の価額が残っているじゃないか」と思われるでしょうが、Aさんは物件購入時に自己資金に加え、信託銀行から10億円ほどの融資を受けていました。
もうお分かりだと思います。相続時には相続財産の価額から負債(マイナスの相続財産)の金額を引くことができるので、結果的に課税価額を2,826万円まで減りました。

「伝家の宝刀」といわれる財産評価通達総則6項
相続財産の評価は税務申告でも面倒な作業ですが、相続税法の第22条には「財産の価額は時価によるものとし、時価とは課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額はこの通達の定めによって評価した価額による」とあります。
つまり基本的には時価なのですが、一般的に不動産の評価は国税庁が定めた「財産評価基本通達」に記載されている、路線価と固定資産税評価額による評価を準用しています。
ところが財産評価基本通達の総則第6項に(この通達の定めにより難い場合の評価)という表題があり、そこには「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」 と書かれてあり、今回の更正処分は「この相続税申告の評価額は著しく不適当だから、国税庁長官の指示を受けて評価した結果」ということになります。
判決翌日の新聞には「国税【宝刀】にお墨付き」の文字が踊りましたが、つまりは「国税当局がダメと言ったら、適法にみえる申告にもケチがつく」ということです。
もちろん相続人が裁判に訴えた内容を要約すると「財産評価基本通達のとおり申告したのに、更正処分は納得できない」ということで、「評価における平等原則に反する」という主張でした。
最高裁判所の判断
この裁判は相続人が税務署の更正処分を不服としておこした裁判なので、原告は「追徴課税を受けた相続人」で、国税庁側が被告になります。判決内容を先にいうと原告の主張は退けられ「国税当局の勝訴」となりました。
「評価における平等原則に反する」という原告の訴えにたいし、最高裁は「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではない」と判断し、更正処分は不適当ではないという内容です。
この判断については最高裁がポイントを示しており、要点をまとめると以下の4点となります。
① 駆け込み的な対策だった点
被相続人Aが金融機関に相談してこのスキームを始めたのが90歳(平成20年)のときで、最高裁は「被相続人及び上告人らは、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる」としました。
②明らかに相続税対策だった点
国税庁はこのスキームが明らかな相続税逃れだった理由として、「金融機関から相続財産圧縮の効果の説明を受けていた」「金融機関の融資稟議に節税対策と記載されていた」「被相続人と金融機関は、不動産2棟の購入及び借入の目的が相続税の節税であると認識していた」という点をあげ、最高裁は「本件購入・借入れが行われなければ本件相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであった(中略)上告人らの相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきである」としています。
③相続後すぐに不動産を売却した点
この点は不動産を用いた節税で「気を付けるべきこと」なのですが、資金繰りのせいなのか相続発生の9か月後に相続した不動産を売却していました。
④多額に租税回避している点
申告時に相続税が0円で、過少申告加算税を含むとはいえ更正処分で3億円近い追徴課税をされるという、あまりにも落差が激しい点も判決に影響を与えています。
最高裁は判決文で「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべき」と述べています。
判決が出たが残ってしまったモヤモヤ
過度に相続税を節税する「タワマン節税」に、伝家の宝刀を抜いた国税庁の判断を追認したような判決ですが、相続税に携わる関係者には今一つスッキリしない思いが残りました。
それというのも、先ほどのポイントで解説した「駆け込み」や「明らかな節税」、そして「大きすぎる節税」について、どこからがダメなのか明確に示されなかったからです。
つまりこれから相続税の節税を考える場合、やることのできる限界を手探りで見つけていかなければなりません。

相続時に確定申告が必要になるケースとは?最高裁判断を踏まえて考える相続税対策
この最高裁判決は大きなインパクトを与えましたが、恐らく一番影響を受けたのは「タワマン節税」というスキームで利益を上げていた金融機関や不動産屋でしょう。
いっぽう税務に携わるものとしても、不用意な相続税へのアドバイスはリスクを伴うという緊張感がでました。
過度な節税に待ったをかけたこの判決を踏まえ、これからの相続税対策をどうしていくべきか考えていきましょう。
不動産を使った節税の全部は否定されていない事実
この判決を極端に受け止める向きも一部ではあるようですが、この事例は極端すぎた点を割り引いて考えるべきです。最高裁判断の4つのポイントがあまりにも鮮明すぎた案件なので、これまでどおり相続税の申告で不動産の評価は、路線価や固定資産税評価額で大丈夫でしょう。
ただ気を付けるべき点も明らかで、「タイトなタイムスケジュール」「購入原資に借入金がある」「不動産の購入が節税以外の目的がない」「購入者が近いうちに被相続人となる高齢者」などのケースは慎重に考えるべきです。また相続開始から少なくとも3年は相続不動産を処分しない点は、これまで同様注意すべき事項です。
どこからが「不相当」になるのか?
さて最高裁が言うところの「看過し難い不均衡」という節税(脱税)とは、どれくらいの金額なのでしょうか。明確な判断が示されていないので、いまは「国税庁が見逃す範囲」としか言うことができません。
これには様々な意見があり、なかには「路線価・固定資産税評価額が購入価格の50%以下ならダメなのでは?」という声もありますが、それも推測にすぎませんし、数億円の案件と数千万円の案件を同列には語れません。
今回の判例では借入金も原資にした不動産購入だったので、上でも触れたとおり「借入金の有無」は大きなポイントになるでしょう。
まとめ
2022年4月19日に最高裁で出された「相続税更正処分等取消請求事件」の判決ですが、一部では「富裕層に激震」といった報道もされています。
たしかに庶民目線でいえば「金持ちの税金逃れ」のようなものですが、相続に関係するものにとっては非常に大きな影響を受ける内容でした。
ただ一つ言えることは、この判決をもって従来の申告方法が全て否定されたわけではないので、変に委縮することなくこれからも相続に関与していく必要があります。